予防は最良の治療 |

◆「治す医療」から「防ぐ医療」へ虫歯になって痛みがでてきてから歯医者さんを受診する方がほとんどだと思います。しかし虫歯ができて削ってしまった歯、歯周病で溶けてしまった顎の骨は完全には元に戻りません。歯科治療も「治す医療」から「防ぐ医療」に変わり、治療が必要になる前に、治療が終わった後も予防することがとても大切です。予防治療とは、その名の通り「歯や口腔内のリスクを予防する医療」です。歯磨きでは落としきれない虫歯の原因となるミュータンス菌の膜(バイオフィルム)を落としたり、虫歯のなりやすさをチェックしたり、定期健診を行うなど様々です。 8020運動の「80歳になっても20本自分の歯を保ちましょう」を目標に、いつまでも自分の歯で食事を楽しめるよう、今から予防歯科を始めましょう。 |
様々な予防治療 |

◆ブラッシング指導毎日朝・昼・晩ときちんと歯磨きをしていても「磨いている」と「磨けている」では大きな差があります。歯の表面はもちろん、歯と歯の間、奥歯の裏や噛み合せ面はきちんと磨けていますか?ブラッシングをしていても虫歯が絶えないという方は、是非一度歯ブラシの選び方やブラッシングの指導を受けることをお勧めします。 また歯ブラシでは磨きにくい歯間も、デンタルフロスや歯間ブラシなどを使って効果的なプラークコントロールをしましょう。歯磨き後にはデンタルリンスや洗口液などを使用すると更に効果的な虫歯・歯周病予防ができます。 |
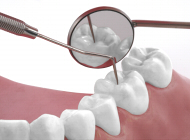
◆歯周病検査歯周病治療は、腫れ・出血・痛みなどの歯周病の症状がある場合は、まず症状を抑えるための処置をしますが、そうでなければ、最初に歯周検査をしてその後の治療計画を立てることから始めます。炎症を起こしている部位や汚れの付着しやすい箇所など口の中の状態を知ることで、その後の治療やプラークコントロールをより効率の良い効果的なものになるからです。 |

◆歯周ポケット歯と歯ぐきの間の溝の深さを測定します。・深さ2mm以内なら健康な歯茎 ・3~5mmなら中程度の歯周病 ・6mm以上なら重度の歯周病と診断されます。 |

◆歯の動揺度ピンセットで歯を揺らしてグラグラしていないか検査します。ぐらつきが大きい場合は、歯周病によって歯槽骨(歯を支える骨)が吸収されていることが考えられます。 |

◆歯ぐきの状態歯ぐきの色や腫れ、出血の有無をチェックします。健康な歯ぐきはきれいなピンク色で引き締まっていますが、炎症が起きると赤みを帯び、ブヨブヨしています。 |

◆顎の骨の状態歯の動揺が大きく歯槽骨(歯を支える骨)の吸収が考えられる場合など、場合によってはX線写真などでの更に詳しい検査が必要なこともあります。 |

◆口腔内写真撮影検査普段は見る事のできないお口の中を撮影し、歯石や虫歯、詰め物などのお口の状況をご覧いただけます。細部まで検査致しますので、見えにくい個所にあった虫歯の早期発見にもつながります。また、治療説明だけでは分かりにくいことも、お口の中をご自身の目で確認していただくことで、分かりやすくご説明致します。 |
 |
